戻 る
第1章 二宮尊徳の生い立ちと生涯の概略
Ⅰ 尊徳はいつ生まれ、いつ亡くなったのか。出生及び終焉に関して
1 尊徳の出生と終焉の日付と場所
出生 天明七年七月二十三日(1787年9月4日)、相模国足柄上郡栢山村で生まれる。
終焉 安政三年十月二十日(1856年11月17日)、下野国今市で満六十九歳の生涯を終わる。
2 尊徳の出生と終焉の場所の概要
出生地の栢山村は、現在の神奈川県小田原市の栢山地区であり、酒匂川中流域の西岸に位置する。現在は、小田急電鉄にも「栢山」という駅があり、栢山地区は、小田急電鉄の線路と酒匂川に挟まれた位置にある。
栢山村は、当時は、小田原藩の知行地であり、出生地には、現在は「二宮金次郎の生家」という建物がある。
尊徳が生まれた頃の酒匂川は、荒れ川であり、たびたび氾濫していたようである。
終焉の地の今市は、現在の栃木県日光市今市地区であり、当時は、徳川幕府の直轄地(天領)で、日光街道の宿駅であった。
3 尊徳の出生と終焉の時代背景
尊徳が誕生した天明という年号の時期には、鬼押し出しの奇観を創り出した天明三年の浅間山の大噴火、それと共に訪れた天候異変、大飢饉という、自然界における大きな異変が続いた。
また一方では、尊徳誕生の前年まで、大奥と結びついて、将軍家重の小姓から側用人、老中と出世した田沼意次が、権勢を振るっていた時期でもあった。
尊徳誕生の年には、松平定信が老中に就任し、その翌々年には年号が「寛政」に変わり、定信による「寛政の改革」が始まるのである。
尊徳が終焉を迎えた安政時代も、地震、風雨などの災害が多く発生した時期である。
安政元年十一月には、四日に「安政東海大地震」、五日に「安政南海大地震」が発生し、七日には九州と四国の間の豊予海峡を震源地とする大地震が発生するなど、僅か四日間に東海地区から九州にかけての広範な地区で、大きな被害をもたらす地震が発生した。
翌安政二年十月には、八丈島近海を震源地とする大地震が発生して、江戸近郊で大きな被害を出した。この地震では、尊徳が居住していた今市近辺でも大きく揺れたようであるが、大きな被害は無かったらしく、翌十月三日の日記に、「昨夜九ツ過地震有之、家内不残外に出、須臾して寝伏申候。但し江戸表邊大地震にて、町家御城等悉く潰候由に御座候事」とあり、十月五日の日記には、「御知行所(※桜町陣屋管轄地のこと、筆者注)邊地震余程大地震之様子、乍併潰家、又は火事等一切無御座候、何等之変も之無由に御座候事」とあり、今市、桜町共に、揺れは大きかったものの、被害は殆ど無かったようである。
その上、安政三年八月二十五日には、台風が関東地区を襲い、江戸が洪水の被害をこうむっている。この時のことは、安政三年の日記の日付部に、「八月二十五日 夜大風雨江戸表津浪大風破損之風聞」とあり、大きな被害の様子が、風聞となって伝わってきていたことが判る。
(※日記の文は、いずれも二宮尊徳全集第五巻「日記下」から引用)
このように、三年の間に、関東から九州にかけての広範な地区で、自然災害によって大きな被害を受けていたのである。
一方政治の面では、アメリカ、ロシヤ等の列国が開国を迫って来航し、鎖国政策の見直しが求められ出していた。国内においては、尊皇攘夷の思想が拡大し始めてきた時期である。
Ⅱ 尊徳の家族はどのようになっていたのか。家族構成に関して
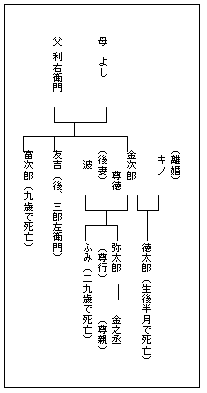
尊徳は、父「利右衛門」母「よし」との間に長男として生まれている。父が三十五歳、母が二十一歳のときである。
寛政二年(1790年)弟の友吉が、寛政十一年(1799年)次弟富次郎が生まれる。
友吉は、長じて親戚の三郎左衛門の家系を継ぐこととなって、養子となり、後に、二宮三郎左衛門を襲名する。
次弟富次郎は、文化四年(1807年)、養育してもらっている親戚の家で、九歳で死亡する。
父の利右衛門は、寛政十二年(1800年)に四十八歳で死亡し、母のよしは、享和二年(1802年)三十六歳で死亡しているので、尊徳は、両親よりも二十年以上長生きすることとなった。
尊徳の最初の結婚は、文化十四年(1817年)二月、三十一歳のときであり、相手のキノは十九歳であった。
二年後の文政二年(1819年)一月、キノとの間に長男が生まれるが、子供はすぐに死亡し、尊徳の仕事が多忙なこともあいまって、キノは尊徳の許を去る。
翌文政三年(1820年)四月、十六歳の波と再婚する。
文政四年九月、嫡男弥太郎が誕生し、文政七年(1824年)七月、長女ふみが誕生する。
波は、多忙で不在がちな尊徳の留守を預かって、二人の子供を成人させた、気丈さがある女性である。
彼女は、明治維新後も生存し、明治四年七月に六十七歳で死去する。
嫡男の弥太郎尊行は、母の後を追うようにして、同じ明治四年の十二月に五十一歳の生涯を終えている。
弥太郎は、父親よりも、母親よりも遥かに若い年齢で生涯を終える結果となっている。
娘のふみも短命であり、嘉永五年八月に尊徳の門人の富田高慶と結婚したが、翌嘉永六年、妊娠を契機に体調を崩し、三十歳の生涯を終えている。
尊徳夫妻の二人の子供は、いずれも、夫妻よりも短く生涯を終えているのである。
尊徳の孫に当たる金之丞は、尊徳の死去の前年、安政二年十一月に誕生し、尊徳にその姿を見せている。
金之丞は、相馬家の庇護を受けて福島県で農地開発の仕事に従事するが、やがて、北海道に渡り、現在の中川郡豊頃町において広大な土地の開発の指揮を執っている。
戻 る
Ⅲ 尊徳はどのような人生を送ったのか。略年表
天明七年(1787年)七月二十三日 金次郎尊徳が誕生する。
寛政二年(1790年) 四歳 弟の友吉が誕生する。
寛政3年(1791年)八月 五歳 暴風雨により酒匂川が氾濫、父利右衛門所有の田畑の多くに土石が流入したことから、耕作不能の荒れ田畑となり、家計が困窮する。
寛政十一年(1799年) 十三歳 次弟の富次郎が誕生する。
寛政十二年(1800年)九月 十四歳 父 利右衛門が死亡する。享年四十八歳。更に貧困が進む。
享和二年(1802年)四月 十六歳 母 よしが死亡する。享年三十六歳。
弟、友吉十三歳及び富次郎四歳は母方の実家、曽我別所村の川久保家に引き取られ、尊徳は、父方の伯父、萬兵衛方に引き取られる。
享和三年(1803年) 十七歳 友達から菜種五勺を借り、実家の荒れ田に蒔き付け菜種八升の収穫を得る。油屋で菜種一升に付き二合の油と交換する。
同年、他の農家が放置した田植えの残り苗を拾って、実家の荒れ田の内の水の溜まった場所に植えつけて、秋に一俵の収穫を得る。
それを、村内の農家に預ける。翌年以後も同様にして収穫を得る。
文化元年(1804年)二月 十八歳 独立を目論み、現金収入を得る目的で、伯父、萬兵衛方を出て、同じ栢山村の名主、岡部伊助家に奉公。
余暇には、勉学と実家の荒れ田畑の起こし返しを進める。
文化二年(1805年) 十九歳 岡部伊助家を出て、同じく栢山村の名主、二宮七左衛門家に奉公替えをする。
文化三年(1806年) 二十歳 預けている米が五俵となり、資金も蓄積できたので二宮七左衛門家を出て、荒れ果てた実家に戻り、一部を改修して住まい、
父が質流れをさせた田畑、九畝十歩(二百八十坪)を買い戻す。以後、少しずつ田畑を買い付ける。4月俳号「山雪」句会参加
文化四年(1807年) 二十一歳 小田原藩士岩瀬佐兵衛家ほかに、日雇いで勤め、金銭収入を得る。
曽我別所村の川久保家に引き取られていた弟、富次郎が死亡する。
文化七年(1810年) 二十四歳 この年には、一町四反五畝余の田畑を所有し、生活にも余裕が出る。
十月には江戸を見学に出かけ、十一月には、伊勢から京都、奈良、大阪、琴平にまで視察を行い、戻ると、自宅の改修を行う
文化九年(1812年) 二十六歳 小田原藩家老(千二百石)服部十郎兵衛家に若党として勤める。嫡男清兵衛の修学の供をして、「四書五経」などの講義が
漏れ聞こえてくるのを聞いて、勉強する。
文化十一年(1814年) 二十八歳 弟友吉が曽我別所村の川久保家を出て、尊徳の家に戻り、自家の農業に従事する。友吉、二十五歳の時である。
三月、服部家に勤務する人たちを対象として、資金の融通を行う組織、「五常講」を立ち上げる。(服部家では「林蔵」と呼ばれていた。)
文化十二年(1815年) 二十九歳 二月、服部家での勤務を辞める。
十二月、服部家の家政困難を見て、その取り直し案を策定して、提出する。
文化十三年(1816年) 三十歳 正月、弟 友吉が二宮三郎左衛門の養子となり、尊徳の家を出る。
文化十四年(1817年) 三十一歳 二月、中島弥之右衛門の娘、キノと結婚する。
文化十五年・文政元年(1818年) 三十二歳 三月、服部家の懇請を受けて、建て直し案の実行を開始する。そのために、再び服部家に頻繁に詰める。
小田原藩主大久保忠真、寺社奉行(享和・四・一・二八―文化七・六・二五)、大阪城代(文化七年六・二五―一二・四・十六)、
京都所司代(文化一二年四・十六―文政一・八・六)を経て、八月二日、老中に就任する。
十一月、老中就任のため小田原を通過する際に、領内の殊勝な人々五十人程を集めて表彰。尊徳も選ばれて表彰を受ける。
文政二年(1819年) 三十三歳 服部家の家政再建のために、頻繁に服部家に詰める。
一月、長男徳太郎誕生するが、二月に死亡する。 三月、妻キノが尊徳の許を去る。
文政三年(1820年) 三十四歳 四月、飯泉村岡田峯右衛門の娘、波と再婚する。
九月、小田原藩主大久保忠真は領民の将来に役立つ提案を、広く募集し、尊徳は、年貢収納用量枡の改善を提案し採用され、十月、枡を作成する。
十一月小田原藩下級藩士向けの救済組織、「五常講」を立ち上げる。
文政四年(1821年) 三十五歳 正月伊勢神宮に参宮、高野山に参拝する。
八月、大久保家分家の宇津家領地の再建に関し、方策樹立のために尊徳外二名が選ばれ、調査のため「桜町」領に派遣される。
尊徳は、報告書と共に引受け条件を提示する。
九月、嫡男弥太郎尊行が誕生する。
十月、小田原藩が内々に尊徳の引きうけ条件を容認する。再度桜町へ、この時、尊徳による仕法が実質的に開始されたようである。
文政五年(1822年) 三十六歳 三月、尊徳の条件付宇津家領地の再建方策が採用され、忠真から正式に文書で尊徳に実行依頼がある。
小田原藩から、俸禄高五石(十一俵余)、二人扶持(九俵)の名主役格を得て、八月二十九日栢山村を発って桜町へ正式に赴任する。
十一月、本格赴任の準備のため、栢山村へ戻る。
文政六年(1823年) 三十七歳 三月、田畑は三反を残して全て売却し、居宅、家財を売却した資金とを併せ持って、妻波と弥太郎と共に桜町に移住し、
本格的に桜町領の再建・復興に邁進する。
文政七年(1824年) 三十八歳 七月、長女ふみが誕生する。
文政九年(1826年) 四十歳 五月、御組徒格(士分)に取立てられ、組頭格となる。
文政十年(1827年) 四十一歳 十二月、小田原藩士豊田正作が桜町陣屋に着任し、尊徳の事業進行の支障となる。
文政十一年(1828年) 四十二歳 四月、小田原藩の武州領地が上地となり、それに伴って尊徳は,郡奉行支配下から大勘定奉行支配下に所属が変わる。
豊田正作らの事業の妨害に悩み、同月辞職願を提出するが、認められず。
文政十二年(1829年)四十三歳 一月、江戸出府の後、三月まで音信不通となる。
農民達が尊徳帰任のための行動を起こし、江戸に出掛け、宇津家に訴え出て認められる。尊徳は、成田山に参篭し、断食修行の後、
大勢の桜町領の農民達の出迎えを受けて桜町へ戻る。
三月二十一日、豊田正作、小田原藩から召還命令を受け、桜町陣屋から離任する。
天保二年(1831年) 四十五歳 宇津家仕法満期となるが、五年間延長する。
小田原藩主大久保忠真、日光東照宮参詣の帰路、結城に宿泊、尊徳らに面会する。
天保四年(1833年) 四十七歳 三月、青木村仕法開始。桜川取水堰完成させる。
全国凶作のため飢饉となるが、尊徳は、早めに対応策を指示し、桜町は、無難に過ごす。
天保六年(1835年) 四十九歳 豊田正作、今回は、本人が希望し、尊徳の事業の協力者となって再赴任してくる。
茂木・谷田部藩細川家仕法開始する。
天保七年(1836年) 五十歳 全国的に凶作で飢饉となるが、桜町は十分な備蓄あり。
十一月、烏山藩大久保家へ仕法を前提として、大量の食糧支援を開始する。
天保八年(1837年) 五十一歳 小田原藩主大久保忠真の命により、藩主手許金千両及び藩の米蔵の在庫を元に、小田原藩内で困窮者の救援に当たる。
三月二十八日、尊徳の最高の理解者で、支援者であった大久保忠真が死去する。
宇津家桜町領、第二期仕法が満了となる。
天保九年(1838年) 五十二歳 二月、小田原藩足柄下郡鴨宮の三新田に仕法開始。年末には、小田原領一円への仕法命じられる。
十一月、大磯の川崎屋孫右衛門の仕法を開始する。
下館藩石川家の仕法開始する。
天保十年(1839年) 五十三歳 富田久助高慶が入門する。
天保十一年(1840年)五十四歳 伊豆韮山の代官、江川太郎左衛門からの招聘があり、韮山を訪れ面談する。要請により、多田弥次右衛門へ資金を貸し付ける。
天保十二年(1841年)五十五歳 七月、江戸繁昌記の作者「寺門静軒」、烏山藩家老菅谷八郎右衛門に伴われ、桜町に尊徳を訪れ、数日逗留し、
尊徳の思想の集大成への協力をする。
天保十三年(1842年)五十六歳 後に遠州(現在の静岡県西部地区)での、尊徳方式の農村振興を指導する安居院庄七、桜町を訪れ入門希望し、逗留する。
水野越前守の呼び出しにより、総勢二十八人で江戸へ向う。 二十俵二人扶持の御普請役格で幕府に召抱えられる。
最初の仕事として、利根川分水路見分目論見作成を命じられ、印旛沼の現地を視察し報告書を作成する。その後、大生郷村復興検分命じられる。
天保十四年(1843年)五十七歳 一月、大生郷村現地を視察、報告書提出する。
七月、御勘定所御料所陣屋手付を命じられる。元江川太郎左衛門手代、町田時右衛門随身する。
天保十五年・弘化元年(1844年)五十八歳 四月、日光神領荒地開拓調査見込提出の命令を受ける。
中村藩相馬家の百八十年間の資料を基に、分度を確定する。
弘化二年(1845年)五十九歳 一月、江戸大火発生し、芝、田町五丁目の海津伝兵衛別宅の日光神領荒地復興事業目論見書及び仕法雛形作成事務所も類焼する。 尊徳の各種重要書類消失する。
十一月、中村藩相馬家領地に仕法を開始するため、富田高慶を派遣する。大沢政吉(福住正兄、後に、箱根の発展に尽力、二宮翁夜話著者)が入門する。
弘化三年(1846年)六十歳 二月、下館藩、一部の村から仕法を開始する。
六月二十八日、日光神領復興目論見関係書類六十四冊を幕府に提出する。
七月、小田原藩が仕法を廃止する。
弘化四年(1847年)六十一歳 五月、真岡代官山内總左衛門手付きとなり、二十四日宇津家稽古場を出立、二十六日、真岡・東郷着。
二十七日、大崎神社別当神宮寺仮寓開始する。
弘化五年・嘉永元年(1848年)六十二歳 九月十七日、尊徳家族全員、駕籠で桜町を出発、真岡を通り東郷陣屋に移転する。
十二月、遠州の地で、岡田佐平冶、安居院庄七義道の指導の下、牛岡組報徳社(後の大日本報徳社の母体)設立する。
嘉永三年(1850年)六十四歳 一月、江戸在留中の嫡男弥太郎江戸引揚げ、桜町へ移る。
十月、大沢政吉(福住正兄)尊徳の門を去り、箱根旅館福住家に婿入りする。
嘉永五年(1852年)六十六歳 四月、弥太郎(三十一歳)、鉸子(十七歳)と結婚する。
八月、長女ふみ(二十八歳)、富田高慶(三十八歳)と結婚する。
嘉永六年(1853年)六十七歳 二月、日光奉行所手付けに転属する。病を押して日光神領内を巡察・回村する。
六月、ペリー、浦賀に入港する。
七月七日、長女ふみ(二十九歳)病死する。
九月、安居院庄七、岡田佐平治等今市に来訪、教えを受ける。
嘉永七年・安政元年(1854年)六十八歳 二月、嫡男弥太郎、御普請役見習を拝命する。八月、岡田良一郎(後に、大日本報徳社設立)入門する。
安政二年(1855年)六十九歳 四月二十四日、家族全員で東郷陣屋出発し、その日は徳次郎宿に宿泊、二十五日、今市陣屋に入居する。
箱館(函館)奉行から、蝦夷地開拓を遂げられる門人三人を選び、名前を提出せよとの内意があるが、人手不足につき辞退する。
十一月、孫、金之丞誕生する。
安政三年(1856年)七十歳 二月、御普請役(三十俵三人扶持)昇格の下命あり。(三月四日の日記記載)
十月二十日、巳中刻(午前十時頃)死去。
戻 る
第二章 二宮尊徳が実施した事業と業績の概要
Ⅰ 尊徳は、どのようなことを行ったのか。実施した事業に関しての概要
ここで取り上げる事業は、尊徳が、自分の家業としてではなく、主として他の人々の利益のために行なった事業である。
その事業には、一農民としての身分の時期に行なった事業と、小田原藩に取り立てられた後の時期に実施した事業とがあるので、ここでは、その区分に従って表示する。
また、小田原藩取り立て後の事業においては、その事業の客体、事業内容、指導者、関与の程度が異なるので、それらの区分を表示することで、全体の事業を単一の形態で表示した。
1 事業実施時期の区分
(一) 小田原藩取り立て前(一農民時代)
文化九年、数え歳二十六歳で、小田原藩家老服部十郎兵衛家に若党として勤め始めてからの時期のことである。
それより前の時期の活動は、あくまでも尊徳自身の資産形成に寄与する活動が殆どであり、他者への貢献を目的とした社会的な事業活動は、この時期から始まる。
(二) 小田原藩取り立て後(名主役格、御組徒格、幕臣御普請役格、御普請役時代)
文政五年(1822年) 尊徳が数え歳三十六歳のときに、小田原藩で名主役格に取り立てられてから、死亡するまでの時期である。
取立ては、小田原藩の分家筋に当たる宇津家の領地、桜町領の復興再建の指導者として活動させる目的であったが、紆余曲折はあったものの、見事に成功させて期待に応えている。
その後、桜町領での復興・再建の成功を聞き及んだり、目の当たりにした人々からの懇請を受けて、大名領、旗本領、その他の地域及び個人の家政の復興・再建事業に本格的に取り組み、輝かしい業績をあげる。
その功績の話がいろいろなルートを通じて幕閣の許に届き、天保十三年(1842年)数え歳で五十六歳の時に、尊徳の手腕の活用を目論んだ幕府から、御普請役格の幕臣として登用され、数え歳七十歳で死亡するまで各地、各家の復興・再建に取り組むのである。





